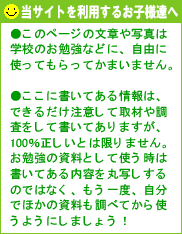|
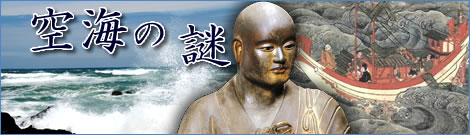
空海についての様々な謎を、初代先達・真魚が突拍子もない発想から 勝手に推測するコーナーです!
もちろん、学術的根拠も一切ありませんので、気楽に、広〜い心でお付き合い頂ければ幸いです!
測量方法について
空海は「太陽の道」を知っていたうえで、長安「青龍寺」を起点とする東の延長線上に、善通寺や高野山を置いたのではないか?
その仮説を考えるうえで、測量方法が問題になります。
そこで笠井さんは、太陽の影を利用した測量について、国土地理院に問い合わせてみました。
国土地理院の担当者は「裏付け資料がない」との理由で、一旦は否定的な見解を示しましたが、それからしばらくして学校宛に「関係文献に触れる機会があり、先の回答を訂正したい」との手紙が送られてきたのです。
その内容は、西洋においては緯度の測定は測地学の分野だが、東洋では天文暦学と結びついており、当時も緯度の測量は分の制度で可能だった、というものでした。
これにより、笠井さんは次に、当時の技術で太陽の影による測量が可能かどうかを実証するため生徒たちに試作器作成の指示をだしました。
生徒たちは見事に期待に応え、見事「太陽の影測定器」なるものを作ることに成功したのです。
木の板に影の長さを計るための棒を立て、重りをつけた糸をたらして垂直を調整することが出来る原始的な器具ですが、詳細はここでは割愛させて頂きます。(※高松工芸高校郷土史研究会の当時の発表資料に図入りで詳しく掲載されています。)
もちろん、この「太陽の影測定器」で、太陽の影による緯度の測量にも実際に成功しました。
核心の謎解きへ
しかし、笠井さんは「大事なことは緯度が同じということではなく、なぜ空海は同じ緯度にこだわったのか。」であるとして、その謎解きに向かっていきました。
次回に続く
|